ギターにはエレキやアコギなどさまざまな種類があるが、基本的にどのギターも弦の本数はなぜか6弦である。
もちろん7弦などもっと弦の本数の多いギターもあるにはあるが、弦のセット売りにしても6本セットだし、ほとんどのギターが6弦が常識になっているのは間違いないところだ。
これには何か理由があるのだろうか?
今回は、ギターの弦の本数はなぜ6弦なのかについて見ていきたいと思う。
ギターの弦の本数はなぜ6弦?
ギターの弦の本数は今でこそ6弦が基本となっているが、6弦に落ち着くまではかなりの紆余曲折があったものと思われる。
初期のギターは、今のギターと比較して大きさも小さく弦の本数も少なかったが、これが時代とともに弦の本数が増えてきて今の6弦に落ち着いたというのが簡単なギターの歴史である。
ギターの弦の本数が6弦として落ち着いたのは18世紀後半~19世紀といわれている。
この6弦に落ち着くまでの経緯を知れば、ギターの弦の本数がなぜ6弦になったのかを知ることができるはずだ。
まず初期のギターは、弦の本数が少なかったことから音域も今より狭く、コードを鳴らすにしても弦の本数分の音しか鳴らせなかったはずである。
これをさらに発展させるためには弦の本数を増やすことが必要になってくる。
弦の本数を増やすことによってメロディーの音域を広げ、コードも分厚く鳴らせるようになり、結果的に落ち着いた弦の本数が6弦というわけだ。
エレキやアコギでもギターの弦の本数は6弦?
エレキやアコギでもギターの弦の本数は、やはり6弦が基本で、これはギターの種類にかかわらず、ギターの大原則である。
逆に6弦より少なくなると、それはギターという名称では呼ばれなくなり、ウクレレなど別の呼び方をされることになる。
他にはリュートやマンドリンなど、ギターの親戚のような楽器もある。
いずれもギターと似ているが、弦の本数や形状などの違いによって違う呼び方をされている。
これらの弦楽器の中で、ギターが最も種類豊富でポピュラーなものとして広まったが、弦の本数が6弦というのがピッタリの本数だったからというのがひとつの理由としてあげられるのではないだろうか。
弦の本数が6弦以上のギター
とはいえ、演奏する音楽の特性に合わせたり、さらに広い音域の音を出すために弦の本数を増やしたギターも作られている。
弦の本数が6弦以上のギターだと、7弦ギターから始まって、10弦のギター、12弦ギター、18弦ギターなどまである。
音域の広さを目的としたもの、オクターブまたはユニゾンの豊かな響きを目的としたもの、低音弦を増やすことで倍音を均等にすることを目的としたものなどさまざまな効果を狙っている。
クラシックギターではスペインのナルシソ・イエペスが10弦ギターのパイオニアとして知られ、ロックギターではレッド・ツェッペリンのギタリストだったジミー・ペイジが「天国への階段」のライヴ演奏の時に12弦&6弦のダブルネックギターを使用しているのが有名な例だ。
ギターの弦の本数~まとめ
今回は、ギターの弦の本数はなぜ6弦なのかについて見てきた。
まとめると、ギターの弦の本数はなぜ6弦なのかは、まさにギターの発展の歴史そのもので、メロディーの音域の広さ、コードも分厚く鳴らすことができるちょうどいい弦の本数が6弦だったからと推測する。
エレキやアコギなどギターの種類にかかわらず弦の本数は、やはり6弦が基本で、これは、ギターの大原則である。
そうはいっても音域のさらなる広さを追求したり豊かな響きなどを求めて、ギターの弦の本数は7弦、10弦、12弦、18弦ギターなどさまざまある。
今後はどういうギターが求められるかはわからないが、さらなるアイディアを盛り込んだギターが登場することだろう。
※この記事には筆者の個人的見解も含まれています。

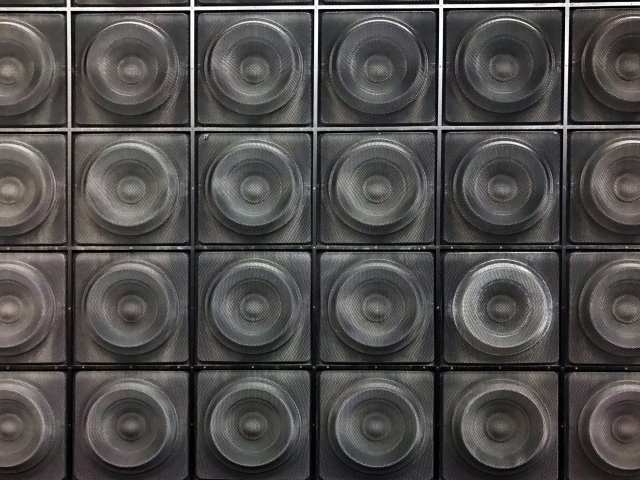

コメント