ギターのバインディング後付けは、見た目のカスタムだけでなく、耐久性や演奏性の向上にもつながる注目のDIY手法です。特に近年では、シールやインレイとの組み合わせによってオリジナリティを演出するアーティストも増え、自作派にも人気が高まっています。
今回は、ギターのバインディング後付けをテーマとして、交換との違いや加工・接着剤選び、トリマーの使い方、さらには費用や注意点まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。これからギターのバインディング後付けに挑戦する方は必見です。
この記事でわかること
- ギターのバインディングとは?その種類と役割
- 後付け・交換の違いと作業の難易度
- 自作・DIYする場合の必要道具と手順
- 料金や費用の目安、カスタム例の紹介
ギターのバインディング後付けの基本知識と準備

ギターにバインディングを後付けする前に、まずはその役割や種類、そして交換や追加の違いについて理解しておくことが大切です。ここでは、そもそもバインディングとは何かという基本から、自作やDIYを行う上で欠かせない道具や注意点まで、準備段階に必要な情報を詳しく紹介していきます。
ギターのバインディングとは?種類と役割を解説
ギターの「バインディング」とは、ボディやネックの縁に取り付けられた装飾的かつ機能的なパーツのことです。一般的にはプラスチックやセルロイド、最近ではウッドバインディングもあり、見た目の美しさだけでなく、ギター本体の耐久性を高める重要な役割も果たします。
バインディングの種類は大きく分けて2つに分類されます。まず装飾性に優れたセルボン系や多層構造タイプ。見た目が華やかで高級感を演出できるため、ハイエンドモデルによく使用されます。次に、実用性を重視した単層のプラスチックバインディング。軽量でコストパフォーマンスも良く、初心者用や中級機によく採用されています。
役割としては、木材の断面を保護し、衝撃や乾燥によるヒビ割れからギターを守る効果があります。また、弾き心地の面でもネックのエッジ部分にバインディングを施すことで、手の滑りが良くなり演奏性が向上します。特に長時間プレイするギタリストにとってはありがたい仕様です。
見た目、耐久性、演奏性の向上と、バインディングはまさにギターにおける縁の下の力持ち。後付けでの追加を検討する際には、こうした機能面も含めて選ぶと満足度の高い仕上がりになります。
ギターのバインディング後付けは可能?交換と追加の違い
ギターのバインディングの後付けは可能です。ただし、既存のギターの構造や塗装状況によっては、作業の難易度が大きく異なります。そのため、「交換」と「追加」の違いを理解することが大切です。
まず交換とは、すでに取り付けられているバインディングを取り外し、新しいものに付け替える作業です。古いバインディングが劣化していたり、剥がれたりしている場合に行われます。元のラインに沿って新しい素材を加工する必要があるため、細かな作業が要求されます。
一方で追加とは、もともとバインディングが付いていないギターに新しく取り付ける作業のことです。こちらは見た目をカスタマイズしたい人に人気で、DIYで挑戦する人も増えています。ただし、トリマーでボディの縁を削ったり、接着剤で固定したりと、工程は多く慎重な作業が必要です。
どちらの方法を選ぶにしても、ギター本体にダメージを与えないことが大前提です。特にビンテージギターの場合は、価値を損なわないようプロに依頼するのが無難です。交換か追加か、自分の目的やギターの状態に合わせて適切な判断をすることが成功の鍵となります。
ギターのバインディングは自作できる?DIYでの注意点と必要な道具
ギターのバインディングを後付けで自作することは、DIY好きにとって魅力的な挑戦です。自分好みにカスタムできるだけでなく、愛着も深まります。ただし、作業にはいくつかの注意点があり、事前の準備が成功のカギとなります。
まず押さえておきたいのは、ボディやネックの加工が必要になるという点です。後付けにはバインディングをはめ込む溝を作る必要があり、トリマーなどの電動工具を使って木材を削ります。ここでのミスは取り返しがつかないため、テスト材で練習してから本番に挑むのがおすすめです。
また、接着剤の選定も重要なポイントです。乾燥時間や強度にばらつきがあるため、作業工程や素材に合わせた接着剤を選ぶことが必要です。たとえば「タイトボンド」や「瞬間接着剤」などがよく使われますが、それぞれ使い方にコツがあるため事前に確認しておきましょう。
必要な道具としては、以下のようなものがあります。
-
トリマー(またはルーター)
-
クランプ(固定用)
-
サンドペーパー
-
接着剤(タイトボンド、瞬間など)
-
ヒートガン(曲げ加工が必要な場合)
-
セルボンまたは木製バインディング材
また、作業スペースの確保と十分な時間を用意することも大切です。焦って作業すると失敗につながります。
DIYでバインディングを自作するのは難易度が高めですが、じっくり取り組めば確実にスキルアップにもつながります。楽しみながら、少しずつ進めていきましょう。
トリマーや接着剤など道具の選び方
バインディングの後付け作業では、使用する道具の選び方が完成度を左右します。特に「トリマー」と「接着剤」は作業の成否に直結するため、慎重に選ぶ必要があります。
トリマーは、ギターの縁にバインディング用の溝を掘るための電動工具です。精密さが求められる作業なので、小型で操作性の高いものを選ぶと良いでしょう。ビットのサイズや種類も確認が必要で、バインディングの幅や深さに応じた刃を使い分けることが基本です。
接着剤に関しては、素材との相性がポイントになります。たとえば、セルボン素材のバインディングには「アセトン系接着剤」が効果的です。一方で、木材同士を接着する場合は「タイトボンド」などの木工用ボンドが定番です。瞬間接着剤も使えますが、位置決めの猶予がないため、慣れていない場合は避けたほうが安全です。
さらに、ヒートガンやクランプといった補助工具も重要です。ヒートガンはバインディングを曲げ加工する際に便利で、特にアコースティックギターなどの曲線部には欠かせません。クランプは乾燥中の固定に必要不可欠で、隙間なく密着させるために複数用意しておきたいところです。
安価な道具で済ませようとすると、仕上がりにムラが出たり、ギター本体にダメージを与えるリスクもあるため、信頼できる工具を選ぶことが成功への近道です。道具にこだわることが、美しく実用的な仕上がりへの第一歩となります。
剥がれや塗装への影響と修理の対処法
バインディングの後付けや交換作業では、「剥がれ」と「塗装へのダメージ」が大きな懸念点です。これらを未然に防ぎ、トラブルが起きた際にも適切に対処することが重要です。
まず、剥がれの原因として多いのは、接着不良や経年劣化によるものです。特にセルボン素材は気温や湿度の変化に弱く、素材が収縮・膨張を繰り返すことで接着面が浮きやすくなります。また、接着剤が適切に選ばれていなかったり、クランプ不足によって密着できなかった場合にも剥がれが発生します。
一方で、塗装への影響は作業中に最も気を付けたいポイントです。トリマーを使って溝を掘る際や、接着剤のはみ出しを拭き取る際に、既存の塗装を削ってしまうケースが少なくありません。特にラッカー塗装は繊細で、アルコールや接着剤に弱いため、養生テープや保護フィルムでギター全体をしっかり覆うことが重要です。
剥がれが発生した場合は、再接着を行います。まずは剥がれた部分を丁寧に清掃し、古い接着剤を取り除きます。その後、適切な接着剤を使用して再度圧着した後、クランプでしっかり固定し、24時間以上乾燥させると安心です。
また、塗装の剥がれや欠けが起きた場合には、タッチアップ用の塗料や透明ラッカーを使って補修できます。広範囲にわたる塗装ダメージがある場合は、プロに依頼するのが最善です。
ギターのバインディング後付けの実践方法と応用
バインディングの知識を押さえたら、いよいよ実践です。実際の作業には加工手順の理解はもちろん、道具選びや費用の見積もりも欠かせません。ここでは、バインディングの取り付け方法から、失敗しやすいポイント、さらにネックやボディごとの巻き直しのコツ、カスタム例まで、応用的なノウハウをまとめて紹介します。
実際の加工手順と作業時間の目安
ギターにバインディングを後付けする作業には、いくつかのステップがあり、それぞれに時間と集中力を要します。以下に一般的な加工手順と、それにかかる作業時間の目安を紹介します。
まず初めに行うのはギター本体のマスキングです。塗装の保護や切削ミスを防ぐため、マスキングテープで作業部位以外をしっかり覆います。これに10〜20分ほどかけて丁寧に行いましょう。
次に、トリマーを使って溝を掘る作業に入ります。深さや幅を一定に保ちつつ、バインディング材に合わせたサイズに調整していきます。この工程は最も神経を使うため、30〜60分は見ておくと良いでしょう。事前にテストカットを行うことも大切です。
その後はバインディング材の曲げ加工と仮合わせを行います。アコースティックギターなどの曲面部分には、ヒートガンを使用して柔らかくしながら少しずつ形を合わせていきます。これには30〜40分ほどを見込んでください。
仮合わせができたら、接着剤を塗布して圧着します。タイトボンドや瞬間接着剤を均一に塗り、クランプやテープで固定します。乾燥には最低でも6〜12時間、できれば24時間かけるのが理想です。
最後に、はみ出した接着剤の処理や研磨、仕上げ塗装の補修を行います。ここでも30分〜1時間ほどをかけ、全体の見た目を整えましょう。
トータルで見ると、作業時間の目安は8〜12時間程度ですが、乾燥時間を含めると丸1日以上を想定しておくと無理がありません。初心者が挑戦する場合は数日に分けて少しずつ進めると安心です。
費用・料金の目安とセルボン素材の価格
ギターのバインディング後付けを検討する際に、気になるのが費用面です。材料費から工具代、場合によっては工賃まで、全体のコストを把握しておくことで、計画的にカスタムを進めることができます。
まず、セルボン素材の価格ですが、これはバインディングの幅や長さ、層の数によって異なります。一般的なセルロイドバインディングであれば、1mあたり300〜800円程度が相場です。装飾性の高い多層セルボンや特殊なカラーのものは1,000円を超えることもあります。
必要な長さは、ギターの形状によって変わりますが、エレキギターであれば2〜3m、アコースティックギターでは4m以上必要になる場合もあります。そのため、材料費としては1,000〜3,000円程度が目安です。
次に、工具費用です。DIYで行う場合、トリマー(10,000〜20,000円)や接着剤(500〜1,500円)、クランプ(1本500円前後×複数)、ヒートガン(2,000〜5,000円)などが必要になります。すでに所有していれば追加費用は発生しませんが、初めて揃える場合は合計で20,000円程度かかることもあります。
一方、プロに依頼する場合の相場は、1カ所のバインディング追加で5,000〜15,000円程度、全体を巻くフルカスタムでは30,000〜50,000円以上になることもあります。塗装の補修が含まれる場合はさらに費用が増加します。
目的や予算に応じて、セルフで行うかプロに依頼するかを選びましょう。見た目と性能を両立させるためにも、コストをしっかり見積もることが成功の第一歩です。
成功のポイントと失敗例|いらない工程とは
バインディングの後付け作業を成功させるには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。一方で、無駄な手順や誤った工程を避けることも、完成度に大きく影響します。
まず、成功のポイントとして最も重要なのは下準備の丁寧さです。作業前にギターをしっかりと清掃し、作業範囲を正確に測定することで、加工ミスを防ぐことができます。特に、トリマーで溝を掘る前のマーキングは慎重に行いましょう。
次に、道具の精度と使い方も結果に直結します。安価な工具を使ったり、正しく扱えない場合は、ギター本体に傷をつけてしまうリスクが高くなります。使い慣れた工具や、信頼性の高い製品を選ぶことが安心です。
また、乾燥時間を守ることも大切です。接着剤はしっかり硬化するまで動かさず、最低でも一晩は置いておくようにしましょう。これを怠ると、せっかく取り付けたバインディングが後から浮いてしまう原因になります。
反対に、よくある失敗例としては「塗装を削ってしまった」「曲げが足りずにひび割れた」「接着剤がはみ出して仕上がりが汚れた」などがあります。こうした失敗は、準備不足や焦りから生まれることが多いです。
そして見落としがちなのが、「いらない工程を入れてしまう」ことです。たとえば、バインディングの幅に合わない深さで溝を掘る、必要以上にボディ全体を研磨するなど、本来不要な作業は、完成度を下げるだけでなく、ギターの性能にも悪影響を与えかねません。
効率よく、確実に仕上げるには、「何を省略し、何に時間をかけるべきか」の見極めが重要です。情報収集をしっかり行い、自分に合った手順を選ぶことが、理想の仕上がりを実現するコツといえるでしょう。
ネック・ボディごとの巻き直しのコツ
ギターのバインディング後付けにおいて、「ネック」と「ボディ」では作業のアプローチが異なります。それぞれの構造と形状に応じた巻き直しのコツを押さえておくことで、仕上がりが格段に良くなります。
まずネック部分に関しては、フレットに沿って細く長い形状をしているため、繊細な作業が求められます。とくに注意すべきはフレットの際までバインディングを均等に貼り付けること。ここが雑だと、見た目だけでなく演奏性にも影響が出てしまいます。既存のフレットを外してから巻く「完全巻き直し」と、フレットを残したまま作業する「部分巻き直し」があり、後者の方が作業は簡単ですが、正確さが求められます。
次にボディ部分ですが、カーブの多いアコースティックギターなどでは、曲げ加工の技術が重要になります。セルボンなどのバインディング素材は、ヒートガンを用いて温めながら慎重に曲げていくことで、滑らかなラインに仕上げることが可能です。曲げすぎると割れたり、戻そうとすると反発で浮きが出るため、少しずつ、時間をかけて調整していくことが肝心です。
また、ネックとボディの接合部(ヒール)では角度が複雑になるため、あらかじめバインディング材を短くカットし、個別に合わせて貼り付ける方法が効果的です。このように、全体を通して「一気に仕上げる」よりも「段階的に丁寧に仕上げる」ことが成功への近道です。
どちらの部位でも共通して言えるのは、接着面の処理と圧着が仕上がりを左右するという点です。作業後は必ず接着の状態を確認し、浮きやズレがあればその都度修正することで、プロ並みの仕上がりに近づけることができます。
カスタム例|シール・ステッカー・インレイで個性を出す
バインディングの後付けは、単なる補強ではなくギターの外観を個性的に演出できる絶好のカスタム手段です。ここでは、他の装飾と組み合わせることで「自分だけの一本」に仕上げる方法を紹介します。
まず手軽に試せるのがシールやステッカーによるカスタムです。バインディングのラインに沿って細いシールを貼ることで、擬似的に装飾を加えることができます。市販のギターデコ用ステッカーは種類も豊富で、剥がしやすい素材が多いため、初心者にもおすすめです。ライブ映えするデザインや、アーティスト風の仕上がりを狙う場合にぴったりです。
次に、インレイとの組み合わせも効果的です。インレイは指板やヘッドに施される装飾ですが、バインディングと調和させることで全体の統一感が生まれます。たとえば、ネックバインディングに沿ってアバロン貝風のラインを加えることで、高級感のあるビジュアルに仕上がります。
さらにこだわりたい方には、バインディングのカラーをカスタムする方法もあります。一般的な白や黒だけでなく、赤・青・木目調など多様なバインディング素材が販売されており、これを活用すれば他とは被らない一本を作ることが可能です。素材によっては塗装でカラーリングすることもできますが、発色や耐久性を考慮して素材選びを行いましょう。
また、アーティストのサインやロゴを模したオリジナル装飾をバインディング付近に追加することで、まるでシグネチャーモデルのような仕上がりにすることも可能です。
これらのカスタム例はどれも自分のスタイルや表現をギターに反映させる手段です。バインディング後付けと合わせて、装飾の楽しさもぜひ味わってみてください。
ギターのバインディング後付けの完全ガイド~まとめ
今回は、ギターのバインディング後付けをテーマとして、交換との違いや加工・接着剤選び、トリマーの使い方、さらには費用や注意点まで、初心者にもわかりやすく解説してきました。
この記事のポイントをまとめます。
- バインディングはギターの装飾だけでなく保護や演奏性向上にも役立つ
- 後付けは「交換」と「追加」があり、目的によって方法が異なる
- DIYでの自作は可能だが、トリマーや接着剤など専門的な道具が必要
- トリマーは小型・高精度なもの、接着剤は素材に合わせて選ぶのがポイント
- 作業ミスによる剥がれや塗装へのダメージに注意が必要
- 加工には準備〜乾燥までトータルで8〜12時間以上かかることが多い
- 費用はDIYで約2〜3万円、プロ依頼では最大5万円以上かかる場合もある
- 成功には丁寧な下準備・適切な乾燥時間・工程の見極めが不可欠
- ネック・ボディで巻き直しの方法が異なるためそれぞれの対応が必要
- シール・ステッカー・インレイによるカスタムで個性的な仕上がりが可能
ギターのバインディング後付けは、見た目を変えるだけでなく、演奏性やギターの寿命にも影響を与える重要なカスタムです。自作で挑戦する場合は、工具選びや作業手順を正しく理解し、焦らず丁寧に進めることが成功のカギとなります。今回紹介した知識をもとに、自分だけの理想の1本を仕上げてみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


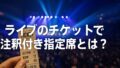
コメント